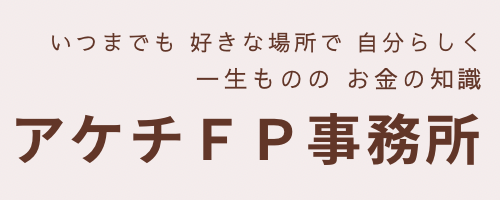年を重ねたり病気やケガによって、それまで当たり前にできていたことが難しくなる。
これは誰にでも起こりうることで、特別なことではありません。
まわりの人の支援や「介護」が必要になることもあるでしょう。
「介護」が必要になったとしても、
介護をする人・される人、どちらか一方が我慢するのではなく、
お互いの生活や思いを尊重し合える関係が理想ですよね。
一人ひとりが自立したうえで、困った時には支え合う。
そんな「介護のかたち」について考えてみたいと思います。
1.介護の始まりや終わりは、予測できない
介護は、ある日突然始まることがあります。
どれくらい続くのか、どんな支援が必要になるのか・・・人それぞれまったく違います。
親と同居している人もいれば、遠方に暮らしている人もいます。
子育てや仕事と両立しながら介護をする人も少なくありません。
だからこそ大切なのは、まわりと比べず、「自分たちがどんな暮らしをしたいか?」を考えること。
「自分たちらしい介護のかたち」で、完璧でなくてもいいので続けていくことが大切です。
2.介護は「その人のできること」を支えていくこと
介護と聞くと「身の回りの世話をすること」をイメージする人も多いのではないでしょうか。
実は、高齢者の介護を社会全体で支え合う「介護保険制度」の基本にあるのは、自立支援という考え方です。
これは、できることを活かしながら、その人らしい生活を送ることができるように支援すること。
「できないことを代わりに行う」という視点だけでなく、
「自分のしたいことや自分のできることを行うための支援」も、介護においてはとても大切です。
そして、そういった支援の方法を一緒に考えてくれるのがケアマネージャーです。
本人や家族の声を聴きながら、その人に合ったプランを立ててくれる心強い存在です。
3.家族だからこそできる関わりもある
家族だからこそ距離のとり方が難しく、遠慮して言えなかったり、
逆につい言いすぎてしまったりすることもありますよね。
本人や家族が、年を重ねる中での変化をなかなか受け入れられず、
お互いの気持ちがすれ違うことも少なくありません。
そんな時には介護のプロの手を借りたり、家族の中で役割を分担したりしながら、
「本人がどんな暮らしをしたいのか?」を一緒に考えていけると、
気持ちも少し軽くなるのではないでしょうか。
- 好きなもの、嫌いなこと、生活のペースなど「その人らしさ」に寄り添った接し方
- 日常のさりげない会話やふとした触れ合いなど、自然なやりとり
- 今まで過ごしてきた思い出を一緒に振り返る時間
気持ちや時間にゆとりがもてたら、家族だからこそできる関わり方が見つかるかもしれません。
4.まとめ
支える側にも日々の生活があるから、心や時間にゆとりを持つのはとても難しいものです。
相手に自然とやさしく向き合えるよう、まずは自分の足元を整えることを意識してみませんか?
そのうえで「自分たちはどんなふうに暮らしたいのか?」を軸に少しずつ話し合うことで、
「自分たちらしい介護のかたち」が育っていくのだと思います。